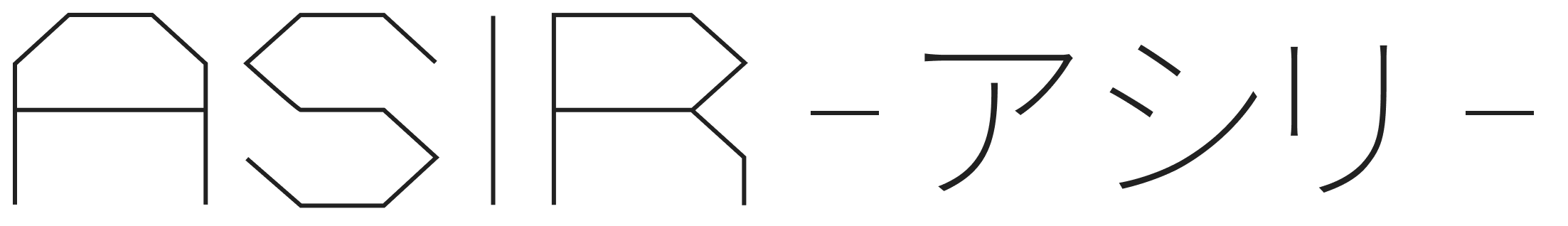個別と集団授業の違い~個別指導を選ぶメリット
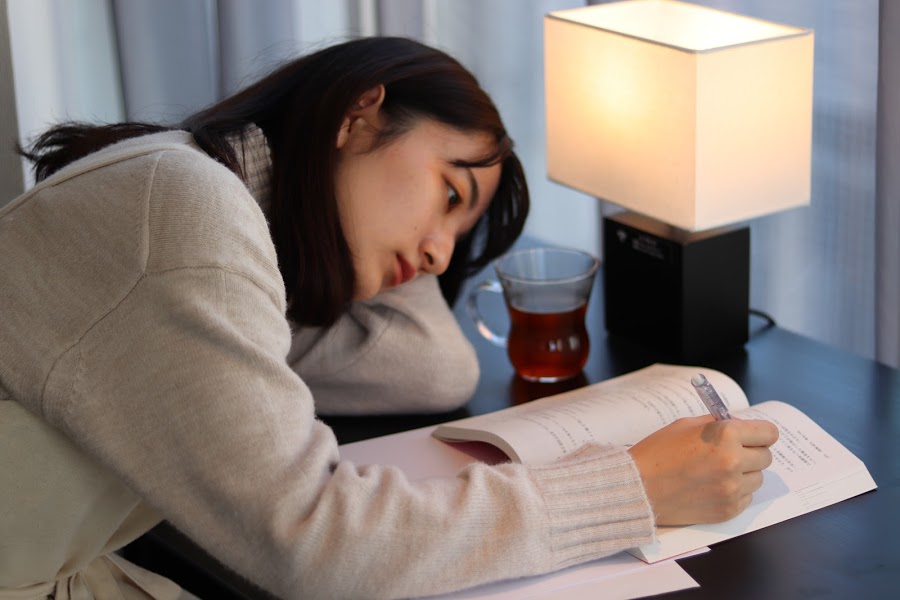
皆さまは、受験勉強の成果を決めるものは何だとお考えですか。
受験勉強の成果は、「学習者の素養 × 学習の質 × 学習時間」で決まります。
個別指導は、この「学習の質」に問題のある生徒さんにとって、有益な指導形態になります。個別指導は、学習の質に直接テコ入れし、その質を上げていきます。
また、自力では充分な学習時間を確保することができない生徒さんにも、有益な指導形態となります。
以下のいずれかに覚えのある生徒さんは、学習の質に問題があるのかもしれません。
・教科書は簡単なので、受験勉強に重要ではないと思う。
・流行りの参考書をたくさん読んでいるが、問題が解けない。
・自分の弱点が分からず、何を勉強すればいいか分からない。
紙面の都合上、これら一つ一つの理由を述べることは割愛しますが、長年の指導経験上こういった考えを持っている生徒さんに問題があるように思います。
さて、では今号では、この「個別指導の特長・メリット」について、いろいろな観点から掘り下げてみたいと思います。
昔からの認識だと、「個別と集団は、同じ。個別は、出来ない子を基礎からフォローアップするだけ」というイメージになるかと思います。
実際、個別指導を、「落ちこぼれの子を基礎から掬(すく)い上げていくもの」だとイメージしていた方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
それらは、昨今では古い認識であると言えると思います。
個別は、双方向的であるということが、最も重要な点です。
集団授業と個別指導の違いは、動画視聴と双方向的授業の違いと同じです。
言い方を変えると、一方向的な集団授業で棄損している点は多いので、それを拾い上げていくのが個別指導です。
本人の学力に合ったことをコントロールしてやって、効率的に、迅速に学力を上げていきます。
業界の中で見ても、本人の学力に合わないことをやって伸びないという事が、多いのです。
勉強を適切な手順でやっていくことが、効果的に、迅速に学力を上げる秘訣となります。
よくいらっしゃるのが、「学生の講師の個別指導塾で教科書をやってもらって、そのあとでアシリで入試問題をお願いします」という方や、「学生の講師の個別指導塾で基礎を固めてから、そのあとでアシリで応用問題を扱ってもらいます」という方なのですが、最初からアシリのプロ講師のところへ来ていただいた方がよいのです。
入試問題や応用問題ができないのは、基礎ができていないからであり、基礎に抜け漏れがあり、基礎の運用ができていないからです。
基礎の抜け漏れを判別するのは、学生の講師(解説を読むだけ)ではできず、プロ講師が必要です。どこが抜け漏れしているか判別できないため、学生講師に基礎固めをさせるという事が、そもそも無理なことなのです。
そのため、最初からプロ講師のところへ来て頂いて、プロ講師に基礎から応用・発展まで任せたほうが効率的です。
理系でいうと、応用問題は、使っている論理の数が多いです。
基本問題は1つの理論しか使っていなくても、応用問題は、3つの論理を組み合わせて解かなければならないのです。
そのため、理解していない論理を的確に見抜いて、手当てしていく必要があります。
それができないと、時間を使っても成果が上がらないと言えます。
それができるのが、個別指導のプロ講師であるといえます。
「アシリに来る前に、現役生のころ、大手予備校に通っていたけれど、大手のハイレベルと呼ばれる予備校の教材が異様に難しく、アシリに移って来て、医学部に合格してから、『大手の予備校の教材のハイレベルな知識や応用問題は(医学部入学に)必要なかった』と思った」という生徒が、実際に、けっこう多くいるんですよ。
大手予備校のテキストには、経営戦略上、大手のブランドとプライドが表れざるを得ませんし、また、教材をかなり難しくしなければならない論理的・合理的理由もあるのでしょう。
ところで、医学部というと、「大手の教材の難しい問題が解けないと受からない」というイメージがありますが、実際にはそんなことはなく、基本を固めておけば受かります。
全国の私立医学部の入試では、教科書に載っているレベルの基本的問題をスピードをもって解く情報処理能力が試されます。
基礎・基本の知識を徹底して覚えられているかが試され、それらの知識を(うろ覚えではなく)充分に吸収していてスピーディーに解けることが求められます。
そのため、医学部入試と言っても、基礎・基本からの出題が7割を占めます。
それなのに、学力に合わない余計に難しいことをやって、(ますます)合格から遠ざかっていく受験生が、毎年多すぎます。
現役生のとき、基本ができていないのに、「大手予備校の信者」になって、ついていけないような難しい問題ばかりやっても意味がないのですよ。
でも、それって、医学部に受かって、ある程度、俯瞰できる立場に立たないと気づかないことでもあるのです。
やはり浪人する前、現役生のころは、視野も比較的狭く、入ってくる情報量も限られているためか、「大手予備校の信者」になりやすく、医学部入試に必要ないレベルの発展的問題の予習復習に追われ、結局ついていけなくなって、学習効果が全く上がらなくなる、という事が少なくないようです。
現役生の心情的な焦りのためでもあり、逆に「大手予備校の難しい問題に挑戦したい。解けるようになったら、グッと志望大学合格が近づくだろう」という現役生ならではの覇気にもよるのでしょう。
でも、大手予備校に通ったあとでアシリに来た受験生たちは、「アシリの先生とのやり取りで固めていった基礎基本で、医学部合格を手に出来た」と口々に言いますよ。
中学受験でも、最高峰の筑波大駒場は、「私立の開成や麻布と違って基礎的な問題が多く、基本を徹底できているかを見ている」とよく言いますが(その分、合格ラインは8割を超えます)、私立医学部もそれと同じく、大学に入ってから医学を学ぶにあたって、つまづくことや落ちこぼれることがないよう、まず「基礎基本を徹底できている受験生」を入学させたいのでしょう。
応用的な事柄や発展的問題は、医学部に入ってから、いくらでも大学で学ぶことができますが、大学に入ってから基礎を学びなおさなければならないというのは、マズいわけです。
アシリの個別指導なら、医学部受験に必要な基礎的事項を、マンツーマンで観点を変えながら繰り返し確認していき、磨きをかけていくので、記憶に定着してすぐに思い出せるようになるほか、少し違った角度から基礎事項が出題されたときにも、素早く対応できるようになります。
この点でも、アシリの完全マンツーマン授業と、120分の充実した授業時間がモノをいうわけです。
アシリやアシリオンラインと、一般的な医学部予備校を徹底比較してみようと思います。
まず、既卒生が、4科目を毎週1コマずつ受講した場合、1週間の授業料(4科目合計)は、アシリやアシリオンラインの場合は60,060円となり、一般的な医学部予備校の場合は、94,600円となります。
アシリに通った場合は、授業料を3分の2以下に抑えることができるのですが、なんとそれだけでなく、この授業料で、アシリは1コマの授業時間が120分と1.5倍なのです(一般的な医学部予備校は、1コマ80分)。
もうこれだけで、全てが表現されつくしているのですが、さらに比較してみると、アシリの授業料は、1か月で240,240円で、一般的な医学部予備校では378,400円となります。
アシリを選べば、1か月あたり、138,160円も節約できます。
さらに、48週受講として年間概算を出してみますと、アシリの場合は、年間授業料が2,882,880円となり、一般的な医学部予備校では年間授業料が4,540,800円となります。
1年間トータルで見ると、アシリのほうが1,657,920円も節約できるのです。
そして、48週受講として年間トータル受講時間を出してみますと、アシリの場合は384時間、一般的な医学部予備校の場合は256時間となり、アシリやアシリオンラインのほうが128時間も授業時間が長いことになるのです。
つまり、最初に1週間で数字を計算してみましたが、1年間を通してとなると、アシリのほうが年間授業料が1,657,920円も節約できるうえ、授業時間は128時間も長いのです。
また、アシリの年間授業料である2,882,880円を、仮に1授業80分で換算した場合、1,921,920円となりますので、一般的な医学部予備校の年間授業料4,540,800円と比較して、半分以下に抑えられることになります。
さらに、アシリは、万全の感染症対策を徹底し(緊急事態宣言の発令中は全てオンライン授業)、リーズナブルな授業料&充実した120分授業の上、完全マンツーマン授業ですし、厳選されたプロ講師による個別指導を実現し、ホスピタリティの高い学習環境をご用意しております。
アシリのプロ講師は、他の有名大手塾・医学部予備校にも在籍経験がある上、合格実績も豊富に兼ね備えています。
また、長年の指導経験に基づいて、「ゴール(合格)から逆算して、いつまでにどこを理解していればよいか」という受験戦略を練ることができる講師を採用しています。
その他、大手ジムの「メガロス」と提携して高校生以上にはメガロス会員カードを無料配布しているほか、オプションで、学習状況や生活習慣の振り返りを毎週行うことができる「オンラインカウンセリング」も好評です。
問い合わせが多く、面談の際にもよく聞かれる「医学部予備校の種類」を解説したいと思います。
本稿では、医学部予備校を、「集団授業」「少人数授業」「個別授業」「トレーナー方式」の4つに分類してみました。
集団授業の予備校は、講義を行う講師を厳選されていて、大手のブランドがあるが、ついていきにくいのがデメリットです。
講師と生徒の距離が近くないため、分からない点がほったらかしで積み残されていくことが起こりうるほか、講師のプライドが高い場合もあり、時間の兼ね合いもあって質問に行きにくい、なんてことも起こります。
でも、集団授業は、周りと競争しながら、環境から刺激を受けて意識が高まってきて、モチベーションが上がるのがメリットです。
「もともと成績がよく、授業以外の勉強も自主的に計画を立てて進められる」タイプが向いていると言えます。
少人数授業は、集団授業と個別授業の間を取っているので、それぞれについてメリットを比較すると負けてしまいます。
多少、環境からの刺激を受けることができるし、多少、自分の理解度に合わせてくれる、と言えばわかりやすいでしょう。
利益率を上げたいけど、面倒見もよくしたいという経営側の思惑が表れています。
「成績をグンと伸ばしたいが、勉強のやり方に自信がない」というタイプに向いています。
次は、マンツーマンの個別授業です。個別授業の小規模校のメリットは、本人の能力に合わせた無駄のない勉強ができることです。
1:1で教えてもらうため、分からない点をその都度質問することができ、理解度が上がります。
また、講師の側では、「1週間の勉強で何をやってきて、どこまで進歩したのか」を把握したうえで、「前の単元ができていないから躓(つまづ)いている」などと分析し、総合的に判断して学習内容を管理することができます。
「自分の学力・理解度に合わせて教えてほしい。なかなか苦手分野が克服できない」というタイプに向いています。
一方、「1:3」の個別授業は合理的に見えますが、学生講師が担当することが多く、生徒が問題を解いているときに観察したことを元に質問を投げかけて、気が付いたことを学習プランニングに反映させていくということができません。
矢継ぎ早に問題への質問に答えているだけで、学習者の本質的に悪い部分を改善することができないのです。
4つ目のトレーナー方式は、自己管理ができない子に向いています。
放っておくと惰性で怠けてしまう子に、細かくアドバイスして、勉強の約束をして裏切らないようにして、トレーナーが「伴走」して、生徒の実行力を上げていきます。
そのため、「自己管理能力が足りず、自分の勉強のやり方を実行できない」というタイプに向いていると言えます。
逆に、大手予備校の集団授業についていける学力と自己管理能力がある子には、トレーナー方式は「いちいちうっとうしい」ということになります。
さて、このメルマガをお読みの皆様は、予備校の経費について、考えたことはありますか。
予備校の経費は、人件費と固定費からなっています。
でも、実際に授業料を払っている生徒様や保護者様が関わっているのは、人件費の部分ですよね。
つまり、合格に最も強い影響を与えている講師の人件費に多くを割くのが、コスパの良さにつながります。
今の時代に合った塾は、講師の人件費に多くを割り当て、その他の固定費(事務、教室代、本部の維持費)などを可能な限り減らして、よい講師を雇う一方で授業料をなるべく安くするようにしています。
では、大手のように事務や教室代に固定費を費やして、合格には近づくのでしょうか。
大手はブランディング戦略の一つとして、好立地のオフィスビルに教室を構えているので、授業料がオフィスビルの固定費に消えていき、実際には合格に近づいていません。
合格とは関連がないのです。
「好立地のオフィスビルの中に予備校があると何となく通いやすい」、「事務や受付のお姉さんがたくさんいると何となく安心だ」という心理的効果を狙ったイメージ戦略(ブランディング)を大手は展開しているのですが、実際には集客につながって大手が儲かるだけで、合格にはほぼ全く関係ないと言えるでしょう。
アシリは、今の時代に合わせて、講師の人件費以外のところを可能な限り削って、それでいて高いホスピタリティーを維持し、大学受験生でも1授業を2時間13,650円(税抜)で提供しています。
アシリがコスパが良く、今の時代に合っていることや、廉価で合格を出している背景がお分かり頂けたかと想います。
知っていると情報リテラシーが高まる、お得なお話をお届けします。
さて、「医学部100人合格」などと謳っている予備校を見ると、いかにも凄そうに聞こえるし、力のある立派な予備校のように見えますよね。
でも、そこには「延べ人数」と「全校舎の合計人数」という2つのトリックが隠されているのです。
まず、「延べ人数」って、知っていますか。そこから話を始めましょう。
たとえば、医学部に合格した人数が10人で、その10人が全員5つの医学部に合格していた場合、「医学部50人合格」とアピールしてしまうことが、一般的な医学部予備校だとあります。
その50人という人数を、「延べ人数」と言います。
予備校の医学部受験の実態としては、一人の受験生が出来る限りたくさん(8~9校)受験します。志望校と併願校しか受けないような高校受験とは、大きく異なる点です。
そして、多くの医学部予備校は、出来る子がいて、一人が8校受かったら、「8人合格」としてカウントしているんですよ。
そのため、医学部予備校が「医学部100人合格」と出していても、実際には15人~20人しか合格していなくて、1人が5つ以上合格しているだけ、という事が大手にはよくあります。
よく見ると、「延べ人数」と小さく書いてあることもあるのですが、これは「延べ人数」のトリックを使っているのです。
さらに、情報のリテラシーがないと、たとえば「10校の校舎全体の合格者数」を、「1校(該当校)の合格者数」のように取り違えています。
ある校舎が「医学部100人合格」と謳っていても、それはその校舎だけの合格者数ではなく、10校くらいの校舎の合格者の合計だという事が、よくあります。
しかも、それは「延べ人数」なんですよ。
本日は、知っていると情報リテラシーが高まるような、大規模校の合格者数が「延べ人数」と「全校舎の合計人数」という2つのトリックによって脚色されている実態を、お知らせしました。