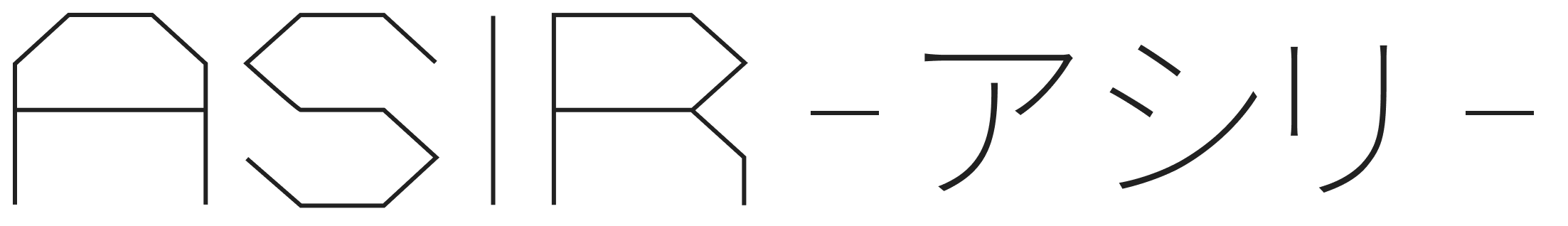セカンドオピニオンとインフォームドコンセント

アシリスタッフのKomabouです。
本日もブログをお読みいただき、ありがとうございます。
つらい時や気分が沈んでいるとき、あるいは気分が落ち着かないときは、笑って明るくなるのが一番ですが、どうしても笑えないときは、「口角(こうかく)を上にあげる」という方策があります。微笑むように口の両側を上にあげるだけで、脳が「幸せホルモン」を出してくれますよ。
本日は、医系小論文や医学部面接を受けるにあたって知っておくと役立つ用語をご紹介します。「セカンドオピニオン」と「インフォームドコンセント」です。
セカンドオピニオンとは、今かかっている主治医以外の医師に求める第2の意見です。
この考え方が広がってきた背景には、従来の「医師お任せ医療」ではなく、インフォームド・コンセント(説明と同意)を受け、「患者自身が治療の決定に関わる医療」に変わってきたという社会背景がありますよ。
つまり、診断や治療選択について、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に求める「第2の意見」を「セカンドオピニオン」と言うのです。
セカンドオピニオンは、今後も現在の担当医の下で治療を受けることを前提に利用するものであり、「セカンドオピニオンを聞く=転院する」ことではありません。
セカンドオピニオンは、以下のようなときに利用することができます。
「担当医の意見を、別の角度からも検討したい」
「担当医の話に、納得のいかない部分がある」
「がんと診断され、治療選択について説明を受けたが、決められない。」
治療を続けるうえで「主治医以外の他の医師の意見も聞きたい」、「他に治療法はないのか知りたい」といった気持ちになるのは当然のことですよね。
希望する治療へ近づくには異なる知見を得ることも大切なのです。
では次は、「インフォームドコンセント」です。
インフォームド・コンセント(imformed consent)とは、「患者が医師から十分な情報や説明を得て、納得した上での合意」を意味する概念です。
医師が充分な説明をし、患者や家族の同意を得ること、 特に、医療行為を受ける人が、治療の内容についてよく説明を受け十分理解した上で、自らの自由意志に基づいて医療従事者と医療方針に合意することです。
医師や歯科医師には、そもそも医療を提供するにあたって充分な説明をする義務があります。
医療法第1条の4第2項では、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と示されています。
インフォームドコンセントは、患者の知る権利、自己決定権を根底にしたもので、セカンドオピニオンと並んで、医の倫理に深く関わっています。
もともと、現在の医学は、ナチス・ドイツの人体解剖から発展してきた暗い影を背負っているのであって、「医師・医療が暴走せず、患者の尊厳を守り、患者の権利を尊重する」姿勢を維持するために、セカンドオピニオンとインフォームドコンセントは重要だと考えられているのです。
また、医師と患者が互いに信頼しあう関係を築くためにも、重要なことだと言えます。
以上の内容、いかがでしたか。
疑問だった点や、聞きたい点があれば、お電話ですぐに対応できます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。