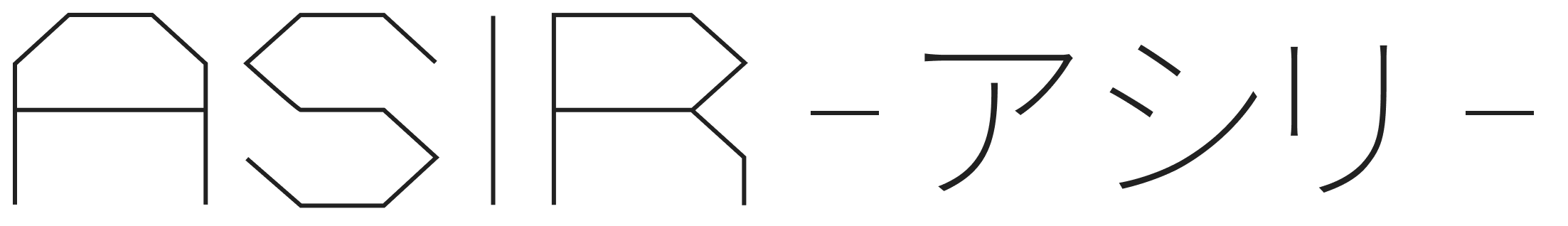医学部・難関大に受かるための受験戦略

長年、医学部・難関大受験生を指導し、何年浪人しても受からないパターンが見てきました。
過去の経験をもとに、この「医学部・難関大受験で成果を出しやすいタイプ」について整理してみます。
何年浪人しても受からないパターンを3つに分類
まず1つ目は、「論理的思考能力が不足し、論理的に考える思考習慣がない」パターンです。
「なぜその式を書いたのか、なぜその結論に至ったのか」を理由や根拠をもって考えることができず、「このやり方で解いたことがあるから」「そんな気がしたから」と、曖昧(あいまい)な記憶だけを頼りに解こうとする傾向が強いパターンです。
以前解いたことのある問題との差異に着目できず、問われている事とは異なる解法を、ただ記憶を頼りに再現してしまうのです。
またこのタイプの人は、知識どうしの繋(つな)がりを考えて広がりを持たせることができません。
そのため、過去に解いた問題と少しでも違う出題だと、太刀打ちできなくなってしまいます。
そして2つ目は、「学習のバランスが悪い」パターンです。
「必要以上に(自分の実力以上に)難しい問題をやってしまう」「特定の教科だけを重点的にやりすぎてしまう」など、学習バランスが悪く、合格点に届かないような配分になっていることに気づかないパターンです。
アシリの入塾面談でも、体験授業の様子、模試の成績、志望大学、これまで使ってきた参考書などを総合的に見させてもらったときに、明らかになることが多くあるパターンです。
3つ目は、「頭はよいが、相応の学習量を確保できない」パターンです。
テキスト批判や講師との議論は熱心にするのですが、言われた宿題をやらずに言い訳が多く、学習の絶対量が確保できていないパターンです。
有名進学校の生徒さんに見られることがあるパターンで、地頭だけで医学部・難関大に合格できるのは昨今では極めて稀です。
では、「医学部・難関大に受かるタイプ」とは、どんな人なのでしょうか。
「毎日一定の学習時間を確保する生活習慣が整っている」ことに加え、「どんなに大変でも、言われた宿題を必ず丁寧にやる」、「毎日決まった時間に遅れずに塾に来る」という規律あるタイプです。
個別指導では、一人ひとりに合った指導法、丁寧なヒアリングやカウンセリング、定期的な面談を通して学習習慣・生活習慣を変えることができ、学習の質を改善することができるので、必然的に良質な学習時間を確保できるようになります。
人生経験が不足しているが故に陥る誤った計画・見積もり
既卒生にありがちなのが、「これまで高校に通いながら、行事や部活の合間を縫って、寸暇を惜しんで勉強してきた。それが丸一年を受験勉強だけに使えるのだから、どこにでも合格できるだろう!」という考えです。実際は、合格点を取るための学習量が考えている以上に多いのですが、その見積もりを誤ってしまうことが多いです。さらに、余計な学習もいくらでも出来てしまうために、大風呂敷を広げてしまい何年たっても受からないパターンに陥ることがあります。
そのため、学習戦略をしっかりと決めて、余計な勉強を極力しないことが志望校合格に必須の考え方です。この取捨選択の作業が生徒一人では難しいために、個別指導でプロ講師がサポートしています。
毎日、計画した時間と量を勉強できる安定した学習が最も結果に影響を与える
もう一つ重要なことは、自己管理能力です。
一般の予備校ですと、毎年一定の割合で、春には猛勉強していた生徒が、夏を境に遅刻や欠席をするようになり、だんだんとルーズになっていくのです。
長い受験生活の中、講義を聴くだけの単調な日々を過ごし、刺激や運動量が減り、段々とモチベーションが下がってくるのです。
また現役合格した友人と会うようになり、大学生活をうらやましく思うあまりに逃避行動をとる生徒も出てきます。
一生懸命に勉強しているほど、結果が出ないときの落胆は大きく、場合によっては引きこもってしまうことさえあるのです。
アシリでは、コーチングを念頭に置き、無駄な解説などは省いて、生徒が求める援助や生徒が必要としている解説だけを行い、授業時間をフルに有効活用しています。
「わかること」と「わからないこと」をきちんと仕分けることが学習効果をあげる
ところで皆さんは、学校の先生や大人から「分かりましたか?」と聞かれて、よくわかっていないのに、または疑問点が残っているのに、「はい、わかりました」と答えてしまったことはありませんか?
これは日本人ならよくあることで、怒られたくないから、自分の能力を低く見られたくないから、面倒くさいことになりたくないから、質問して相手に迷惑をかけたくないから、また場の雰囲気を壊したくないからなど、消極的な心理から起こります。
これは、個別指導の場でも起こりうることで、講師が「分かりましたか?」と聞いて、どこが理解できていないのか分からないから何となく「わかりました」と応えてしまう生徒だと、授業だけが先に進んでしまい、ついていけなくなります。
アシリでは、生徒が「分かりました」と言っても理解が充分ではない場合は見抜くことができますし、生徒がどこが理解できていないのか自分でも分かっていないのに「問題ありません」と言った場合などを察知し、適切にアプローチすることが可能になるのです。
生徒が理解できていないのに、置いてけぼりにして次の単元に進んでしまうという事態も避けられます。
思考力を高められるように指導するのが“アシリの攻めの個別指導”
講師よりも生徒の口数が多くなるような授業を心がけていて、生徒は気になることや分からないことは積極的にどんどん質問して解決していますし、勉強の内容やテキストについても熱い議論が展開されることがしばしばです。
そして、的確な問いかけを通して、生徒自身の気づきや理解、アウトプットを促すような授業が展開されています。
集団授業では講師側からの解説を一方的にインプットするだけになってしまい、理解が充分な所に至らなかったり、すぐ忘れてしまったりという事が起こります。
問いかけを通して生徒側からのアウトプットを引き出していくことで、生徒は頭の中を整理することができますし、また学習内容を忘れにくくなり、他の要素と結びつけて考えやすくなり、問題なく次の単元に進むことができます。
個別指導の良し悪しを決めるのは、授業担当者の能力になります。
生徒数の多い大規模校(大手予備校)は、その授業数に見合うよう講師を大量採用しなければならず、その指導能力にバラつきが出てしまいます。講師の質について目をつぶらなければならないところがある、ということです。
アシリでは、講師の在籍者数を絞っており、能力の低い講師を無理して雇う必要がないのです。大量の講師志望者の中から、当塾で活躍できる講師を厳選しているため、講師陣の能力は群を抜いています。
長年、医学部・難関大受験業界に携わってきた代表が講師を面接採用しているので、むしろ大手よりも質の高い授業を提供できます。
生徒との距離の近さから、運営側も責任感を強く持って任務に就くことができます。
このように、小規模校には、大手や大規模校にはない、強みやメリットがあります。
入試は定期テストと違い、初見の問題は出ないから丸暗記で太刀打ちできない
「学校の勉強も、ある程度やってきた。定期テストの点数も悪くない。だけど、大手予備校の模試の点数が振るわない。」
――このような悩みをお持ちの方は、定期テスト用に丸暗記しているだけで、本質的な学力がついていないという可能性があります。
自分なりに最大限の力で頑張っているつもりでも、どこかでやり方を間違えているようだと、差がつく一方になってしまいます。
正しいやり方とは、「現状の学力に合ったものを正しい手順でやること」です。
このことをきちんと実施するためには、学習者が直面している課題を見極めて正しい手順で取り組ませる必要があるからです。
アシリには、学習者の課題を洗い出し、最適な学習プランニングを提示できる指導経験豊富な講師が在籍しています。
過去に指導してきた医学部・難関大受験生の指導経験から、学習者に合った学習プランをオーダーメイドで作成しています。
その結果、今の自身の学力を見据えて、志望校の合格点のために本当に必要なことだけを厳選し、正しい手順で取り組み、受験校で出題される問題を本番で解けるように「整えて」いくことになります。
つまり、受験校の傾向と難易度を把握し、今持っているリソースも最大限に活かして、ゴールから逆算して最短経路を作るのであって、最低限の努力で医学部・難関大合格がグッと近づいてくることになります。
医学部合格戦略のガイドライン7つの戦術
戦術1 受験校の選定
(1)国公立か、私立か
ご存じの通り、国公立のほうが、私立大学より受験科目数は多くなります。
現状学力に自身がない方や、受験まで差し迫っている方は、科目数の少ない私立大学受験をお勧めします。
(2)難関校か、中堅校か
さらに場合によっては、中堅校を選ぶことによって、出題内容が標準問題中心であったり、記述の割合が少なかったりと、受験準備期間の短い方に好都合である条件が揃うことがあります。
(3)進学後の理想を捨てられるか
受験校を選り好みせずに医師になることだけを考えた場合、ある意味で受験校の選定が重要になってきます。進学後の理想を最優先にして、難関校を何年も受験し続けるリスクを背負えるか、今一度、冷静に見極めることをお勧めします。
戦術2 受験学年までの準備
(1)高2までに、英・数・理科1教科を習得
受験学年になって、慌てて全ての科目をゼロベースで取り組むと勝率は格段に下がります。
受験1年前に、英語、数学、理科1教科の基礎事項を理解していることが望ましい状況です。
この基礎というのは、学校の定期テストで点数が取れている事とは異なります。
受験に必要な基礎事項を習得できているかという事なので、別の見方が必要となり、予備校の模試を判断材料にするのがよいかと思います。
(2)中学生の準備
受験学年から程遠いので、中学生は準備することがないかと言えばそうではありません。
今まで受験生を指導する中で、受験学年までの準備として不足しているものを感じてきたからです。
それは、論理的思考能力と、学習した内容を整理してまとめる力になります。
中学生のうちから、数学、英語、理科等に取り組む中で、医学部・難関大受験に必要な力を養っておくことが実は必要です。
戦術2 受験学年までの準備
(3)地頭を鍛えるコーチング
頭の使い方として、理由や根拠を持って筋道を立てて考える能力の不足を感じる生徒さんがたくさんいます。
特に理系教科でこの点が浮き彫りになります。自覚症状として、誤った解法を次々と乱れ打ちしたり、類題が解けなかったり、学習事項の定着が進まなかったり。
これらは別々の問題のように見えますが、すべて共通の原因です。
こういった学習者の問題点は、マンツーマン指導をしていると気づきます。我々はコーチングを多用し、正しい頭の使い方となるよう、誤りを指摘し気づかせています。
それは、解法を一方的に解説する集団授業では教えることができず、「解法までたどり着く思考回路」をコーチングで定着させています。
(4)読解力が高いと学習のテンポが速くなる
もう1点、受験学年になった際に準備不足を感じるものがあります。それは読解力です。
例えば読むことについては、生徒に教科書を読ませても要点を把握できなかったりします。そうなると、読んだ内容について指導者が都度まとめ直さなければなりません。始終この調子ですと、非効率な学習となり、それだけ受験勉強に時間が必要になります。
【戦術3】 環境からの影響をコントロールする
人は環境から影響を受けるものです。環境によって人格が形成されるといっても過言ではないと思います。
受験勉強においても、この影響を免れることはできません。私の経験上、これによって指導が阻まれたことが幾度となくあります。
(1)在籍校の雰囲気
友人との交友関係によって時間を割かれ勉強不足に陥るという単純なものから、勉強に対する不適切な認識まで、その種類は多岐にわたります。
その中でも最も厄介なのは、自分の目標に見合う努力が、無意識のうちに出来なくなる事です。
なぜなら周りの友人との比較で、自分の努力を自己評価するからです。難関校受験するような友人が少なければ、それに影響され目標に見合う努力を見誤ってしまう可能性があります。
ですから、受験勉強に励む友人を多く作る、医学部・難関大受験に合格した先輩の話を聞く、合格体験記を読む、医学部・難関大予備校のスタッフから学習についての話を聞く、といったことは、好循環を生む環境を整えるうえでとても重要になります。
【戦術4】 生活パターンを作る
学習のスタート時は、やる気にみなぎり、隙間時間も無駄に過ごすことなく勉強に専念できますが、ほとんど長続きしません。
息切れする前に、適度な自由時間を取り入れながら、崩れにくい生活習慣を整えた方がよいでしょう。そのほうが、かえってトータルの学習時間が長くなるものです。
今すぐにでも試行錯誤しながら、自分に合った生活習慣を作るべきです。
また非受験生によく見られることですが、部活が忙しく勉強ができないという相談を受けます。
しかし、全く時間がないわけではありません。時間がないなりの勉強方法があるので、切り替えて短時間で済む学習方法を模索すべきです。
時間管理については、適度な余白を作ること、事前に1日の行動計画を立てて無駄を減らすことなど能率的に過ごすためのスキルはあります。
こうしたスキルを伸ばすことが、受験生活を円滑に過ごすために要求されるので、その練習を早いうちから取り組むことをお勧めします。